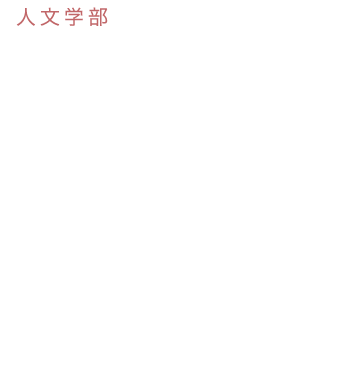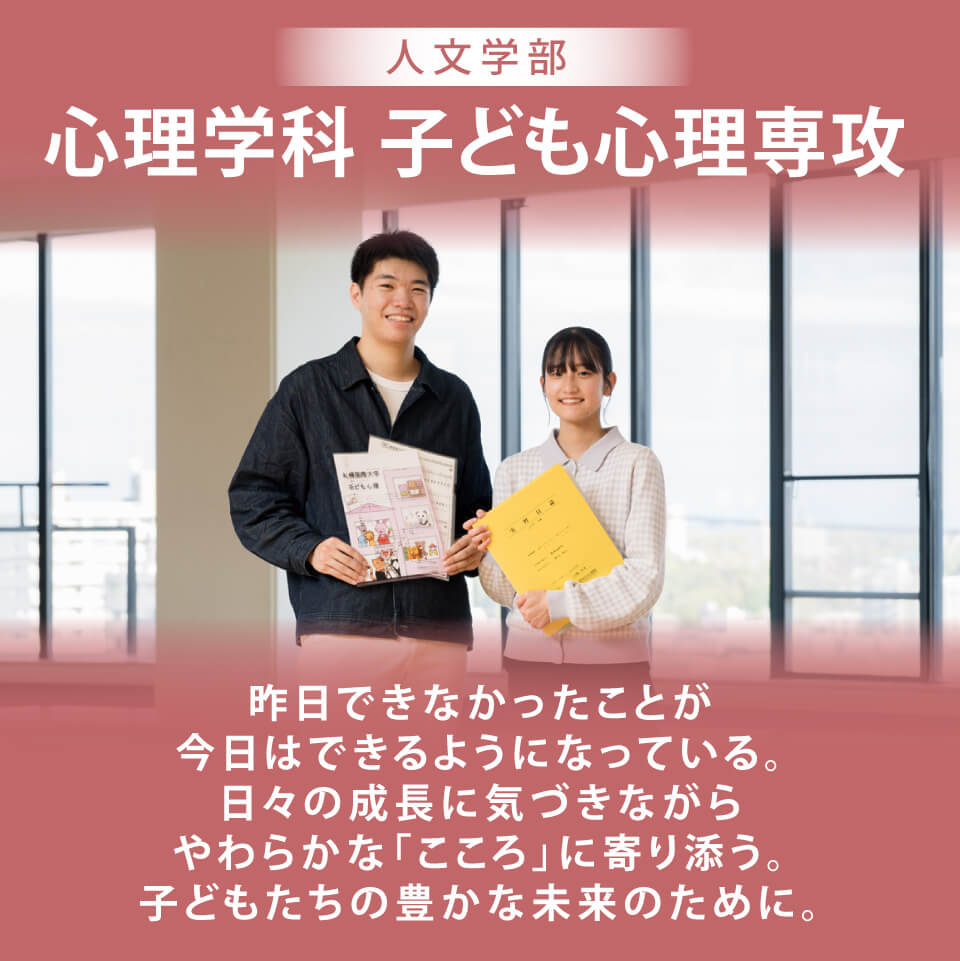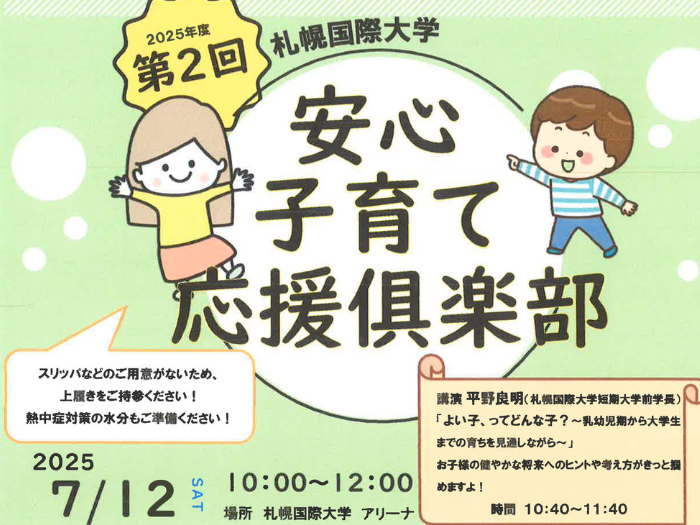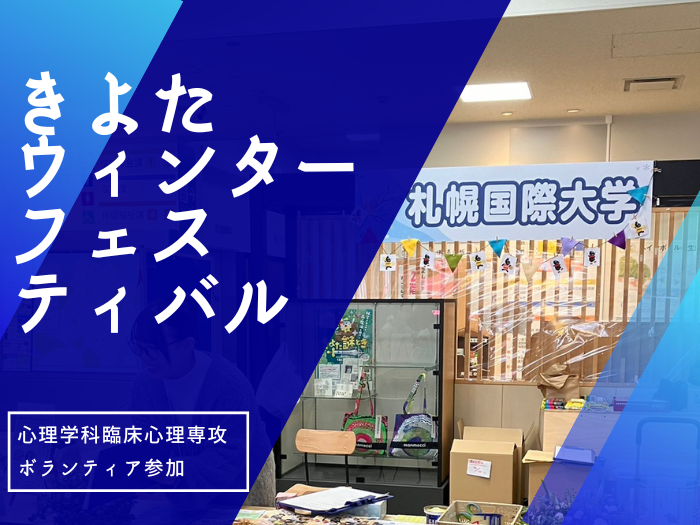NEWS “心理学科子ども心理専攻の新着ニュース”
卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
学位:学士(教育学)
心理学科子ども心理専攻は、所定の期間在学し、所定の単位数を修得し、下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学位を授与する。
- 【専門知識・技能を活用する力】(知識・技能・判断力) (DP1)心理学領域及び幼児教育・保育領域に関する知識・技能を修得し、活用することができる。
- 【コミュニケーション能力】(思考力・表現力・主体性・多様性・協働性) (DP2)心理学を基盤とし、幼児教育や保育、福祉等の現場において、利用者や関係者の理解に努め、自らの考えを適切に伝えることができる。
- 【課題を発見し、解決する力】(技能・思考力・判断力・表現力・主体性) (DP3)幼児教育・保育の現状を分析し、目的や課題を明らかにした上で、適切な手段で計画的に課題解決に取り組むことができる。
- 【多様性の理解と協働する力】(知識・主体性・多様性・協働性・関心) (DP4)幼児教育・保育の場において、年齢、性別、国籍、障がいの有無などの多様性を理解し、適切な対応をすることができる。
- 【能動的に学び続ける力】(思考力・主体性・意欲) (DP5)教育・保育の分野において最新の情報を得る努力を怠らず、より良い教育・保育の在り方を検討し、実践、評価、改善を図りながら継続的に学ぶことができる。
- 【社会に貢献する姿勢】(主体性・多様性・協働性・意欲・関心) (DP6)理想の保育を求め、研究・実践に携わるリーダーとしての自覚を持ち、地域社会に貢献する姿勢を身に付け、その意欲を有する。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
心理学科子ども心理専攻は、学生が卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)で示した資質・能力を身に付けることができるように、以下の方針に基づき教育課程を編成する。
- (CP1)【初年次教育】高等学校から大学への円滑な移行を図るため、能動的に学び続ける力を身に付けることができるように、全学共通教育科目として初年次教育科目を配置する。
- (CP2)【教養教育】幅広く深い教養と総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するため、全学共通教育科目として人文、社会分野を中心に教養教育科目を配置する。
- (CP3-1)【専門教育】心理学領域の基礎的知識を身に付けることができるように、順次性のある体系的な科目配置を行う。
- (CP3-2)【専門教育】幼児教育・保育領域に関する知識・技能の修得のために、順次性のある体系的な科目配置を行う。
- (CP3-3)【専門教育】幼稚園教諭一種免許状及び保育士資格取得のための必修科目、選択科目を体系的に配置する。
- (CP3-4)【専門教育】こども音楽療育士資格取得のための必修科目、選択科目を体系的に配置する。
- (CP4-1)【教育方法】専門知識・技能を活用する力の向上のため、保育施設等において行うフィールドワーク科目や、幼稚園教諭一種免許状及び保育士資格取得のための実習科目を配置し、実践的な学びを展開する。
- (CP4-2)【教育方法】課題を発見し、解決する力や、能動的に学び続ける力、社会に貢献する姿勢を養うため、PBLやグループワーク、フィールドワーク等のアクティブラーニング型の科目と座学科目を組み合わせ、主体的・対話的で深い学びを実現する。
- (CP4-3)【教育方法】多様性を理解する力の向上のため、障がい児(者)理解、障がい児(者)支援に関わる科目を配置する。
- (CP5)【教育方法・評価方法】CAP制により充分な学修時間を確保し、授業時間外の学習を促すことで単位の実質化を図るとともに、明確で客観的な評価基準に基づく厳格な成績評価を実施する。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
心理学科子ども心理専攻は、心理学を基盤とした幼児教育、保育の知識と技能を習得し、時代に合った最善の保育を求めて常に研究を続け、実践に活かすことのできる保育者を育成するために、以下の資質、能力、意欲を持った学生を受け入れる。
【求める学生像】
- (AP1)本専攻での学修に必要な学力を有している人。【知識・技能】
- (AP2)他者の考えを尊重しつつ、自らの考えを他者へ的確に伝えることができるコミュニケーション力を有し、相互理解のうえ協働して学ぶ意欲を持つ人。【主体性・多様性・協働性】
- (AP3)子どもや保育、福祉に関わる諸課題について問題意識を持ち、それを説明・表現できる人。【思考力・判断力・表現力】
- (AP4)教育・保育、心理学の分野に興味・関心を持ち、専門知識と技能を身に付ける意欲を持つ人。 【意欲・関心】
- (AP5)目的の達成に向けて努力することができる人。【態度】
学科の特色
- 子どもの心を深く理解し、適切な支援ができる人材を育成 -
心理学をベースに保育や教育を学ぶことで、子どものこころをより深く理解し、適切な支援ができる能力を身に付けます。また自然に囲まれた本学の広大なキャンパスや施設を利用し、子どもたちと関わることのできる多くのフィールドが用意され、実習だけではなくボランティア活動を通して実践的に学ぶことができます。こうした経験に裏付けられた知識と技術、人間力を備えた質の高い人材を養成します。
学びのポイント
- 心理学をベースに教育・保育を実践的に学ぶ -
- 豊かな教養
- 豊かな社会性
- 豊かな共感力
- 豊かな実践力
- 豊かな専門性
- 豊かなコミュニケーション力
人文学部心理学科子ども心理専攻で目指せる資格
- 幼稚園教諭・保育士などを目指せる -
幼稚園教諭一種免許状
幼稚園教諭になるために必須の免許です。大学卒業で取得できる「一種免許状」は、幼稚園の園長など次代の保育界リーダーになるには欠かせません。
保育士資格
保育士としての就職に必須の資格です。幼稚園・保育所が一元化された認定こども園に就職するためには、幼稚園教諭の免許とあわせて取得することが求められます。
こども音楽療育士
こころ・身体・音楽の相互関係についての知識、楽器の演奏と演奏指導の仕方などを習得し、障がいのある子どもを対象にコミュニケーションを促します。
児童指導員任用資格
児童養護施設などで児童の成長を援助し、生活習慣や学習の指導、生活上のアドバイスなどを行います。指定科目を修了すると取得できます。
認定絵本士
絵本に関わる幅広い知識や技能を身に付けることができます。資格認定後は絵本の魅力や可能性を地域で伝え、読書活動を充実させる役割を担います。
- ■その他の取得目標資格
-
- 教育職員免許状
「小学校教諭二種」(※通信教育)
「特別支援学校教諭一種・二種」(※通信教育)
- 認定心理士
- 園芸療法士
- 社会教育士(養成課程)・社会教育主事任用資格
- レクリエーション・インストラクター
- 教育職員免許状
- ■その他の取得目標資格
-
- 教育職員免許状
「小学校教諭二種」(※通信教育)
「特別支援学校教諭一種・二種」(※通信教育) - 認定心理士
- 社会教育士(養成課程)
・社会教育主事任用資格
- 園芸療法士
- 社会教育士(養成課程)・社会教育主事任用資格
- レクリエーション・インストラクター
- 教育職員免許状
心理学科
子ども心理専攻の授業
PICK UP!
基礎ゼミⅠ

本演習では新入生研修と連動し、大学で生活するために必要な基礎力を身に付けます。札幌市子どもの劇場やまびこ座の方々のご指導を受け、玉人形劇を制作し、清麗祭にて上演します。
子ども心理フィールドワークⅠ・Ⅱ

3~4年次に行う本実習を見据え、さまざまなフィールドで子どもたちと触れ合うことを目的とした1年次の授業です。子どもや保育者を観察して記録を書いたり、実習で使用することを想定した名札などのグッズ制作も行います。
子ども音楽療育実習

音楽を使った楽しい遊びを通して、障がいや発達に心配がある子どもたちの発達を促す療育の方法を学びます。本学を会場に行う音楽療育ワークショップで子どもをサポートしながら理論と実践を繋ぎ、こども音楽療育士の資格取得を目指します。
保育・教職実践演習

保育士資格、幼稚園教諭免許取得を目指す者のための4年次科目です。模擬保育の実施と意見交換を行い、保育を取り巻く社会的課題についての調査、研究を通して、保育者としての使命と責任を自覚し、目指す保育者像を明確にしていきます。
人文学部心理学科
子ども心理専攻の先輩
PICK UP!
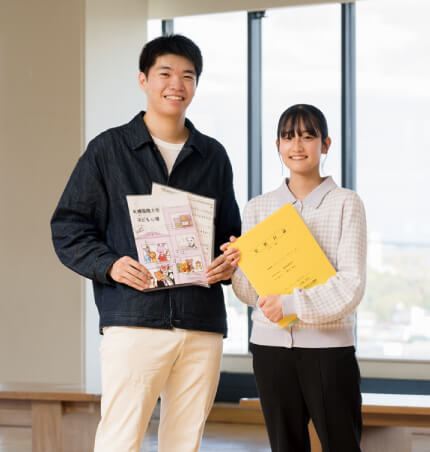
- (写真左)Sさん 清水高等学校 出身
(写真右)Nさん 室蘭清水丘高等学校 出身
Sさん(人文学部 心理学科 子ども心理専攻 3年)
資格も教育環境もサークルも
ここでしか得られない特別感があります
保育の資格に加え、認定絵本士やこども音楽療育士など道内唯一の資格が取れる特別感に惹かれました。毎日教室で保育に関する基礎固めをしながら、多彩なフィールドワークやボランティアを体験できるのも本学科の魅力です。正解のない保育の世界。付属の子ども園や養護施設などで実際に子どもたちと関わりながら経験を積めるのは自信にもつながります。ハンドベルクワイアで特別感のあるサークル活動も楽しんでいます。
Nさん(人文学部 心理学科 子ども心理専攻 3年)
忙しい中に楽しさがぎっしり
先生はもちろん先輩との距離も近いんです
きれいに描こうとする先入観が消え、「子どもの図画工作」では子ども目線でモノづくりする楽しさを再確認できました。保育所や幼稚園だけでなく児童相談所など、保育を取り巻く職場は多岐にわたっていることも教わりました。先輩との縦のつながりが強く、実習先の情報や課題のアドバイスももらえます。子どもの心理をベースに保育が学べる本専攻は、3年になっても時間割はびっしりだけど、忙しさの中に楽しさもぎっしりつまっています。
人文学部心理学科
子ども心理専攻の内定者
Interview

- 人文学部 心理学科 子ども心理専攻 4年
- Nさん
函館西高等学校 出身
【内定先】学校法人函館明照学園 認定こども園高丘幼稚園
資格取得で視野を広げて
学内外で発達支援の
勉強+ 実践
「子ども心理フィールドワーク」など実践的な授業が好きでした。3年次からのゼミでは児童発達支援の勉強をしたり、学外では放課後デイサービスでのボランティアや、児童会館でのアルバイトも続けてきました。現代の保育現場でグレーゾーンの児童への支援は当たり前の課題です。現場では児童への支援だけでなく、その周りの環境づくりや対応の仕方次第でも児童の可能性が変わってくることを目の当たりにしてきました。春からは実習先であり、隣接して学童保育も行う幼稚園で活動していきます。将来は児童指導員の資格も取得し、幅広く児童を支えていきたいです。

- 人文学部 心理学科 子ども心理専攻 4年
- Tさん
市立札幌清田高等学校 出身
【内定先】札幌市(保育士)
よく学び、よく踊り
保育士としての
幅広い学びを吸収して
家族と暮らせない乳児院の赤ちゃんと接したり、養護施設の子どもたちの勉強を見てあげたり、大学でのさまざまな学習を通して、子どもたちの愛着形成の時期をきちんと支える人になりたいと公務員保育士を目指しました。とはいえ、採用試験の勉強は4年次になってから。YOSAKOIソーラン部の活動の合間に、一冊の参考書を徹底的に復習し、幼稚園実習が終わった数日後の1次試験でなんとか合格できました。部活にアルバイトに忙しい4年間でしたが、音楽療育や園芸療法や絵本など、多様な視点を持って保育士になれたのは子ども心理専攻のおかげだと思います。
人文学部心理学科
子ども心理専攻の卒業生
Interview

- 子ども心理専攻 2017年3月卒業
- Aさん
札幌東商業高等学校 出身
【進学先】東橋いちい認定こども園
子どもたちの成長と笑顔に支えられ
自分自身も成長できた
幼稚園実習も保育実習も大変で、大学では保育者に向いていないと投げ出したくなる時期もありました。でも、ゼミの先生の「3年はガンバレ」との言葉を胸に、社会に出てからは「卒園する子どもたちのランドセル姿が見たい」とまた1年、もう1年。気付けばひとつの園で7年が過ぎ、今年からは主任として園の運営にも当たっています。音楽療育士のワークショップでさまざまな子どもたちと触れ合ったことや、心理学の「心のコーチング」の知識も、今の私を支えてくれています。子どもの笑顔と自分の成長を毎日感じられる仕事だから続けられるのだと思います。
人文学部心理学科
子ども心理専攻のカリキュラム
2026年度生用(予定)
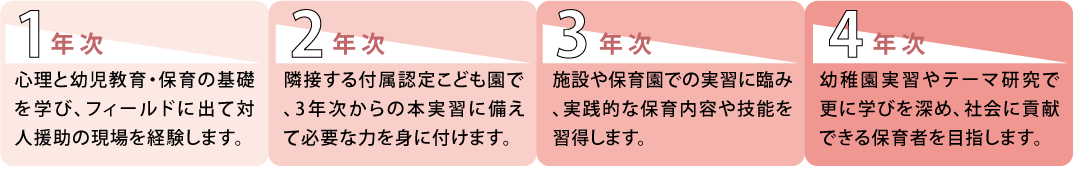
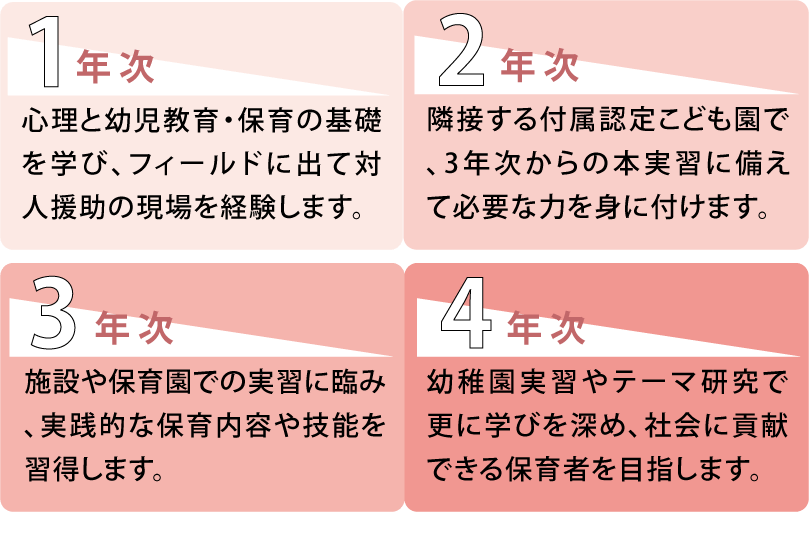
人文学部共通科目
- 1年次
-
- 人文学概論
- 2年次
-
- 基礎演習Ⅰ
- 基礎演習Ⅱ
- 3年次
-
- 応用演習Ⅰ
- 応用演習Ⅱ
- 4年次
-
- テーマ研究Ⅰ
- テーマ研究Ⅱ
- 卒業研究
心理学科基礎科目
- 1年次
-
- 心理学概論
- 社会福祉論
- 心理学実験Ⅰ(基礎)
- ガーデニング演習
- 生活と園芸
- 心理学研究法
- 2年次
-
- 教育・学校心理学
- 知覚・認知心理学
- 発達心理学
- 学習・言語心理学
- 対人関係論
- 色彩心理学
- 心理学実験Ⅱ(応用)
- 心理学統計法
- 障害者・障害児心理学
- 3年次
-
- 感情・人格心理学
- 社会・集団・家族心理学(社会・集団心理学)
- 社会・集団・家族心理学(家族心理学)
- 心理調査概論
- 4年次
-
- 発達心理診断法
子ども心理専攻専門科目
- 1年次
-
- 保育の心理学
- 子どもの理解と援助
- 児童文化
- 教職入門
- 教育原理
- 子ども心理フィールドワークⅠ
- 子ども心理フィールドワークⅡ
- 音楽Ⅰ(歌唱・理論基礎)
- 子どもの図画工作(基礎)
- 保育表現(身体・言葉)
- 保育内容総論
- 幼児と健康
- 幼児と環境
- 特別支援教育
- 2年次
-
- 保育内容指導法
- 子ども家庭支援の心理学
- 子ども家庭福祉
- 保育原理
- 社会的養護Ⅰ
- 教育方法論
- 子どもの保健
- 子どもの健康と安全
- 子ども家庭支援論
- 音楽Ⅱ(ピアノ基礎)
- 音楽Ⅱ(ピアノ応用)
- 子どもの図画工作(応用)
- 保育英語(基礎)
- 保育英語(応用)
- 多文化保育論
- 保育フィールドワーク(海外研修)
- 運動Ⅰ
- 運動Ⅱ
- レクリエーション理論(子ども)
- 幼児と人間関係
- 幼児と言葉
- 幼児と表現
- 乳児保育Ⅰ
- 乳児保育Ⅱ
- 障がい児保育Ⅰ
- 障がい児保育Ⅱ
- 子ども音楽療育概論
- 子ども音楽療育実習
- 3年次
-
- 教育課程論Ⅰ
- 子ども理解の理論と方法
- 子どもの食と栄養(基礎)
- 子どもの食と栄養(応用)
- 音楽Ⅰ(歌唱・理論応用)
- レクリエーション実技(子ども)
- 保育内容(人間関係)
- 保育内容(健康)
- 保育内容(環境)
- 保育内容(言葉)
- 保育内容(表現)
- 子ども音楽療育演習
- 社会的養護Ⅱ
- 子育て支援
- 保育実習指導Ⅰ
- 保育実習指導Ⅱ
- 保育実習指導Ⅲ
- 保育実習Ⅰ
- 保育実習Ⅱ
- 保育実習Ⅲ
- 4年次
-
- 教育課程論Ⅱ
- 教育行財政
- 教育相談
- 保育・教職実践演習(幼稚園)
- 幼稚園実習指導
- 幼稚園実習
- レクリエーション実習(子ども)